20251119第13回地域研究講座を開催しました
今回のテーマ:「岡崎」成立を巡る諸問題ー『新編岡崎市史 中世』の再検討ー
日時、場所:2025年11月19日(水) 14:00-16:30 岡崎市民会館2階大会議室、参加者は会員39人、一般参加者13人で合計52人。興味深いテーマに多数の方が参加いただきました。
まず、司会の奥田副会長による開会の辞と今日のスケジュールの確認が行われました。
14:00-15:30 講義、休憩をはさんで15:40-16:10質疑
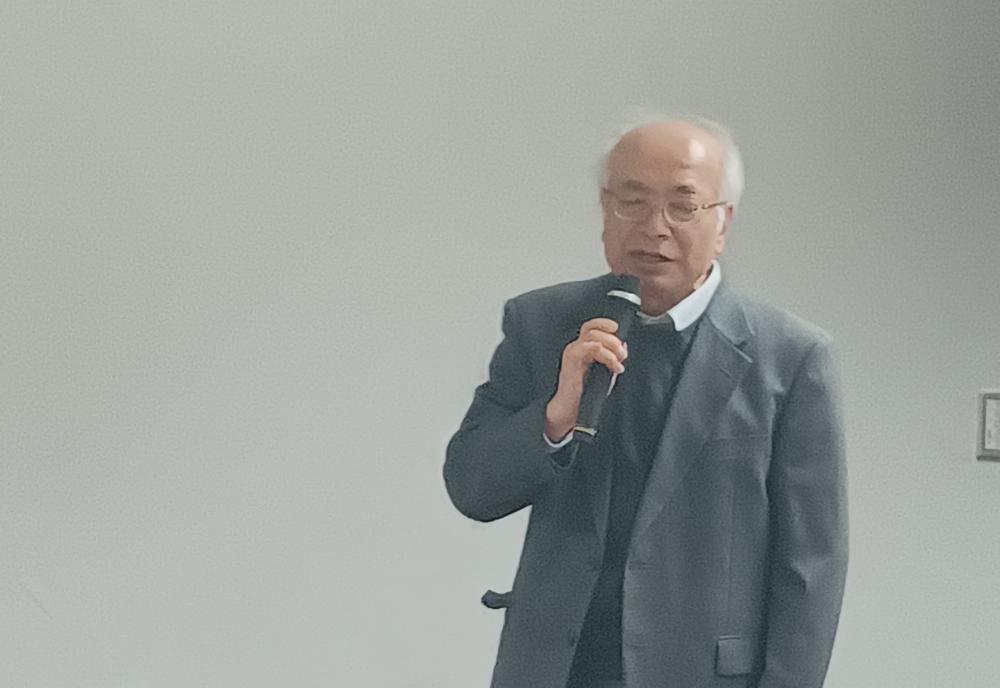
次に嶋村会長挨拶と湯谷祥悟講師の紹介
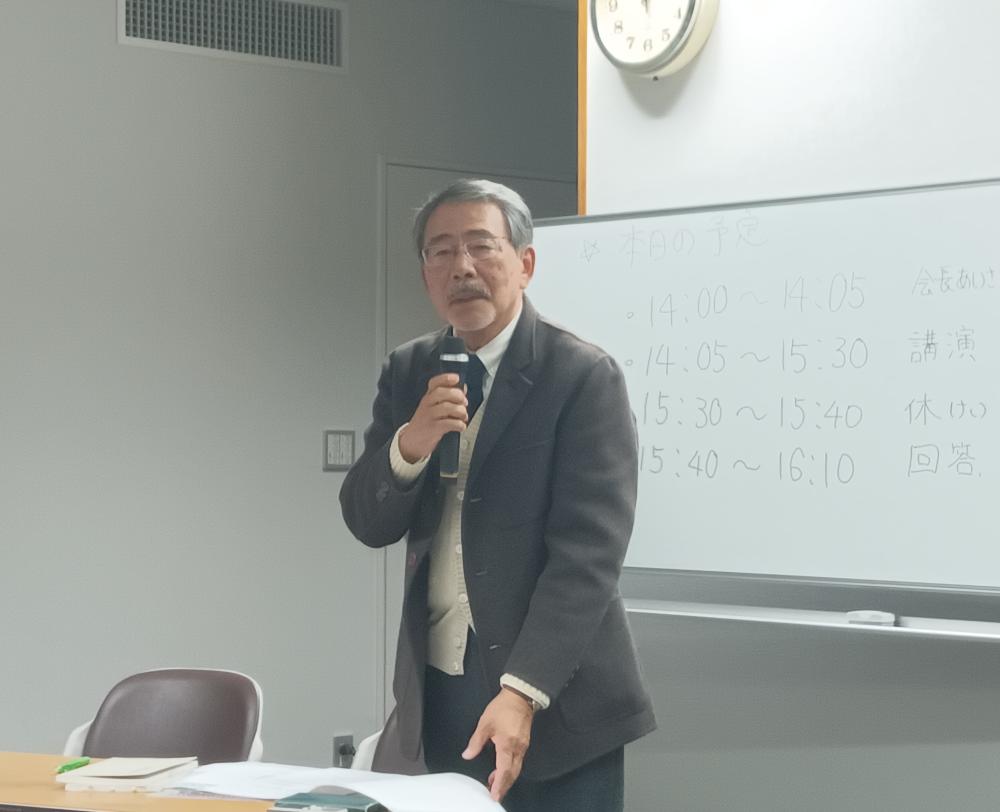
講師は若手研究者として紹介された岡崎市美術博物館学芸員で当会会員の湯谷祥悟さん、不惑の歳になるので若手と言われるとこそばゆいなど講義中にもジョークも交えて資料・史料およびパワーポイントを用いてわかりやすく説明いただきました。

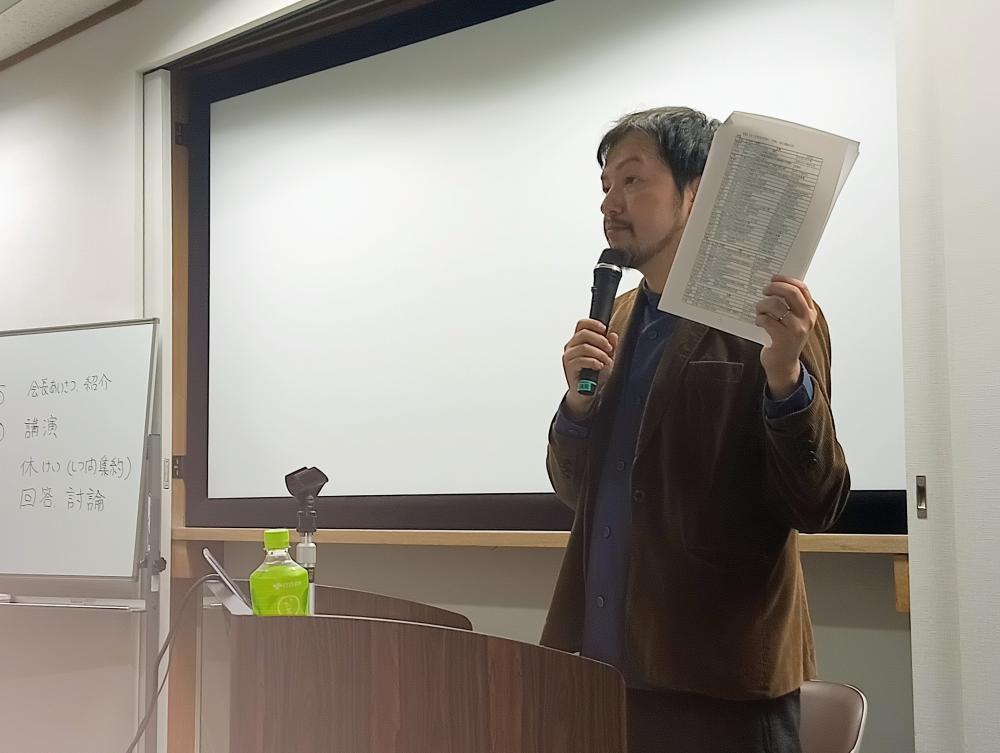

講義内容は1989年に刊行された新編岡崎市史 中世にて述べられている次の三項目について、それ以降に発表された諸研究を精査したうえで新しい解釈を紹介いただきました。
(1) 龍頭山の岡崎城は明大寺の平岩城を移したのでないことを『宗長手記』を見直して説明し、岡崎は乙川北岸とした。。
(2) 田中吉政による東海道の南岸横貫を北岸横貫への付け替えは無い、田中吉政以前に流路変更に沿って南岸から北岸へ縦貫されていた。
(3) 「岡崎」は能見郷の南、菅生郷の中にあった「岡崎」つまり龍頭山の河岸段丘地域。その繁栄により、北岸に菅生郷から分れて岡崎という地域が生まれた。
熱心に聴講する参加者

講義のあとは、参加者からの多くの質問メモを元に湯谷講師と奥田副会長からお答えいただきました。
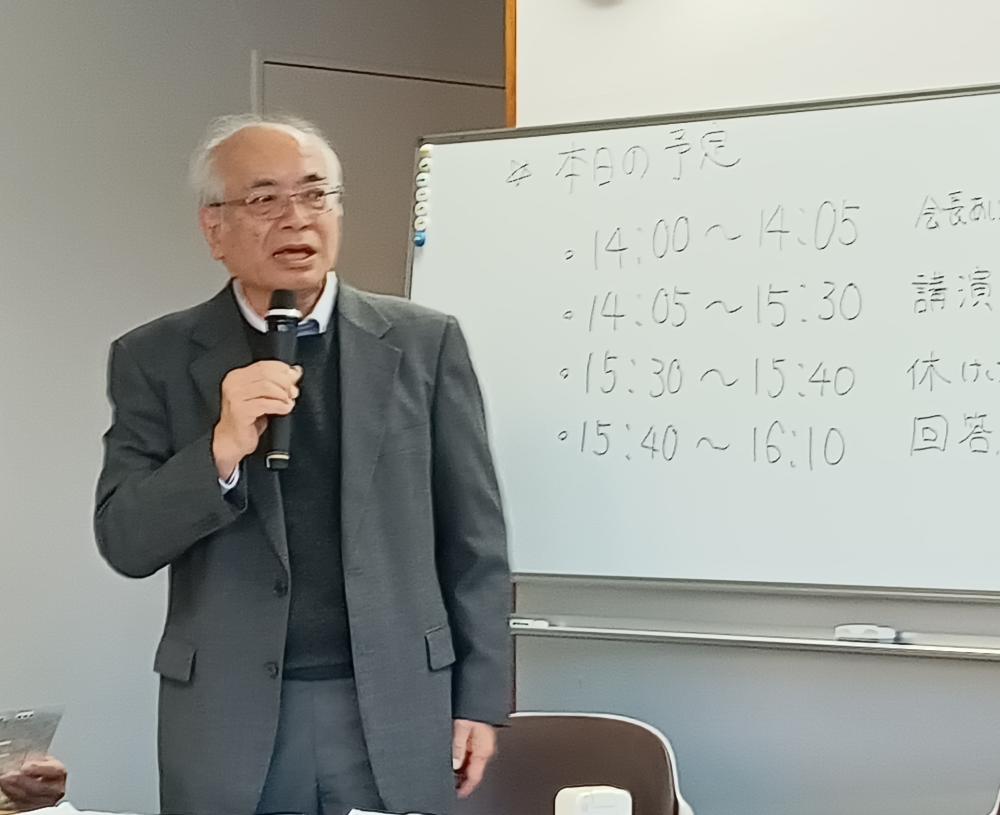

湯谷さん、そして火付け役の奥田さん、長時間の講義・質疑応答ありがとうございました。
なお、講義の詳しい内容は2026年2月に発刊予定の『岡崎地方史研究会便り65号」をご覧ください。
この情報は、「岡崎地方史研究会」により登録されました。